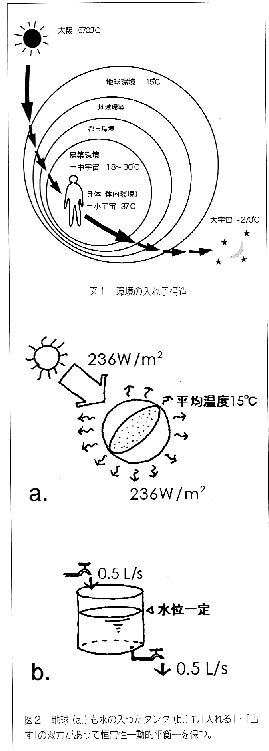専門は建築環境学。
著書に『Exergy:theory and applications in thebuilt environment』(2013年1月、Springer-Verlag London)、『エクセルギーと環境の理論』(改訂版2010年9月、井上書院)など。
天災も自然の営みにほかならないから、これをなくすことは人間には不可能だ。しかし、天災となる自然現象を避けたり受け流したりする…それは可能だろう。そういう生き方・暮らし方を私たち人間が身につけることは、いつの時代にも重要であったに違いない。現代社会はもちろんその例外ではないはずだ。
ところが、自然についての科学的な見方―とは言っても実のところ微視的な見方に偏った見方―が発達した今日の“科学”技術を改めて見渡してみると、技術は全般に巨大化・集中化・一様化の度を増し、その度合いが増せば増すほどに、過去に起きたのと同程度の天災であっても、それに伴って生じる人災の規模はむしろ大きくなる傾向がある。天災としての東日本大震災が引き金となって、ついに起きてしまった原発人災はまさにその一大典型と言えよう。
昔から“衣食足りて礼節を知る”と言われてきたが、この表現には「住」が抜けている。これでは、建築空間の光や熱の振る舞いが軽んじられるわけだ。そう思うことが少なくない。昔の人にしてみれば、住は雨・風が凌げればよく、地の揺れで壊れたら再び建てればよい。そう考えて、住は衣食ほどには意識を向ける対象ではなかったのかもしれない。
しかし、その昔と今は違う。暗ければデンキ(電灯)、暑ければエアコン、寒くてもエアコン…これらが当たり前だと思っている人の数は、建築の素人ばかりか玄人にもたいへんに多い。これら電気・機械仕掛けの技術があるのは人々の意識がそれなりに住に向いてきたからだろうと思う反面、これらの技術は人々の住に対する意識を甚だ浅いレベルに留めさせてしまっている。巨大“科学”技術の端末としてのデンキ・エアコンなどの氾濫は、不自然でない在るべき「住」が設えられてこその本来の明るさや温かさ・涼しさを人々に気づかせないようにする役割を果たしてしまっている。そう思えるのである。
建築外皮の光や熱・空気・湿気に対する諸性質を、住まい手の明るさ・温かさ・涼しさの創出に生かせるようにする。これを現代では「パッシブデザイン技術」と称する。実のところパッシブデザイン技術は建築(環境)技術の基本なのだが、これを重要だと考える人の数はいまだ少ない。それは先に述べた巨大“科学”技術が人々の意識を浅いレベルに留めさせていることと大いに関係していると思う。
パッシブデザイン技術は、建築がその外なる自然と上手に折り合いをつける技術であり、人の内なる自然を健やかに働かせるための技術である。外なる自然と内なる自然をほどよく繋ぐ技術と言ってもよい。筆者はこれまでに携わってきた建築環境の研究・教育の体験を通して、そう考えるようになった。
これでは抽象的すぎて分かりにくいので、例題を挙げて考えてみる。主体を「人」としよう。人は必ずその身体を支えてくれる床・地面の上にあって生活しているので、床や地面は環境の一部である。窓や壁・天井も同じだ。これら壁や床・天井に囲まれた空間、そこには空気が充満しているが、空気もまた環境の一部である。このような主体たる人にとって最も身近な環境を「建築環境」と呼ぶ。
地球の全体は身近ならぬ身遠だが、これを「地球環境」と呼ぶ。その主体は私たち人を含む生物である。「体内環境」という言葉があるが、この場合その主体は人の脳である。体内環境(身体)の調子が悪ければ、仕事が手に付かない…それは脳の働きが鈍るからにほかならないが、そのことを思えば、体内環境の主体が脳であることが納得できるだろう。
地球環境の外側に広がる空間は「大宇宙」と呼ばれることがあるが、素粒子や天体の物理学は、大宇宙の姿を以前に比べれば随分と明らかにしてくれている。そのような物理学の法則で建築環境にも深くかかわって重要なもの一つだけを挙げるとすれば、それは放射(電磁波)の法則だと思う。
放射に関する理論と測定技術はこの120年ほどの間に大いに発達したが、そのおかげで、大宇宙には、およそ140億年前の創成時に現われた放射の名残り―宇宙背景放射―が充満しており、それに相当する温度は−270℃(絶対温度で約3K)であることが分かっている。このような極寒の大宇宙にあって、地球表面全体の平均温度は、私たち人を含む生物が棲むことのできる約15℃という値になっている。それは、太陽が四方八方に放出している放射(電磁波)のごく一部が地球に届いているからだが、その太陽の表面温度は宇宙空間に充満している背景放射の温度−270℃よりも遥かに高い5700℃ほどである。このこともまた放射の理論から明らかとなる。
私たち人の体温はおよそ37℃である。これは、食物の摂取に始まって、体内環境(身体)から建築環境、そして地球環境・大宇宙へと連綿として絶え間なく営まれている放熱によって実現されている。食物の多くは、乾かして燃やせば1000℃を超える炎になる。私たち人は37℃の体内環境で、燃やせば1000℃になり得る食物を恒温動物に共通の特殊な仕方で燃やしつつ、生じた熱の絶え間ない放出によって身体の構造と機能を巧みに維持しているのだ。人体を「小宇宙」と呼ぶわけである。
このように考えを巡らしてくると、建築環境は、大宇宙と小宇宙のあいだに挟まって存在する「中宇宙」と言えるように思えてくる。小宇宙たる人の体内環境は、中宇宙たる建築環境(さらには都市環境・地域環境)・地球環境の内にあり、地球環境は大宇宙の内にある…そのようなイメージである。それを1枚の絵として描いたのが図1だ。筆者はこれを「環境の入れ子構造」と呼んでいる。
くどいようだが、地球表面が吸収する光と、地球が宇宙空間に放出する熱を、図2のa.にそのエネルギー流量率の数値とともに示そう。北極から赤道・南極までの地表面のすべてについて平均すると、1㎡あたりに毎秒236J(=236W/㎡)の光が吸収され、同量の熱が絶え間なく宇宙空間に放出されている。両者があって平均温度15℃は実現されている。
図2のb.は、a.に示した光と熱の出入りを、タンクにおける水の出入りのアナロジーとして描いたものである。蛇口からタンクに入ってくる水が太陽からの光、タンクの底に繋がれたパイプとその先にある蛇口から出ていく水が地球から宇宙空間への熱、タンクの水位が地表面の平均温度に対応する。
入れて出す。地表面の平均温度もタンクの水位も恒常性―動的平衡―が保たれるには「入り」とともに「出」が重要なのである。恒常性は「流れ」のなかにつくられる。人を含む生き物の形態(カタチ)、それらの生き方(カタ)、人のつくる建築のカタチ(構造)とそのカタ(機能)―これらはみな「流れ」があって、その中に現われるのだと考えることができる。
建築環境における光や熱・空気の「流れ」もまた同じである。不自然でない本来の明るさ・温かさ・涼しさは、建築環境空間を貫く「流れ」がほどよいときに初めて現われるのだ。だからこそのパッシブデザイン技術なのである。